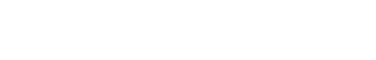花栄寺縁起 鶏谷山花栄寺の歴史
1.はじめに―花栄寺のふるさと探訪
柏崎の中心部から南に向けて国道353号線沿いに車を走らせ、20分ほどもするとゆったりとした黒姫山がなお一層懐深く正面に聳え、炊煙立ち上る野 田の田園風景が広がる。右手には俗称西山と呼ばれる米山の前山が風に揺られたカーテンのように山並みをたなびかせ人々の生活を見守っている。鶏谷山花栄寺 は、失われつつある日本の山里のはずれに居を構え、幾世代にもわたって檀信徒に支えられて今日に至る。現在の住所は木沢だが、しかし最初からここに建立さ れたわけではない。当山25世九里好信和尚様が昭和9年に記した花栄寺沿革史にはおおよそ次のようなことが書かれている。
「古老の語る処によれば、野田村字杉の崎の上位に在ったことがあったとか。この跡を現在も寺屋敷(俗称てらう)とこの地の人は呼んでいるが、何も頼るべき物件も文献も皆無で、年代もまったく不明だから、伝説に過ぎないかも知れない。
次に、野田村字坂又に在ったとの事も古老の語る所であるが、これも又杉野崎同様伝説に過ぎないかも知れない。
又、坂又の次に菅沼の上位に在ったとか、この地には当寺を偲ぶ古井戸があると聞き及ぶが今となっては確認のすべは無い。」(読み下し)
杉野崎、坂又、菅沼と場所を変えてきたという古伝のみあり、その年代、当時の事情をうかがい知ることができないということだ。先年、檀家有志と往時お寺が あったといわれる場所を探してみようと、山田地内の山中に分け入ってみたことがある。エンボン寺という名称だけを頼りに山を登ってゆくと、坂又から谷根方 面に向けて視界が開けるところがあり、その向こうは石切り場であったなどの話を聞いた。付近には山田の人たちがかつてお祭りをしていたという石地蔵があ り、いまはすっかり草生(くさむ)しているが、一昔前までは人間の活動範囲内であったことを伝えていた。花栄寺の原所在地も、そういう今では誰も振り返る ことのない場所で植物が密生し、野生動物や野生に帰化した動物たちが繁殖しているのかもしれない。
2.花栄寺前史―行基菩薩伝説と花栄寺体内秘仏
花栄寺には2つの伝説が残されている。一つは東大寺建立の際に日本全国を遊行し、各地で勧進しつつネットワークを結んでいった行基菩薩につながる伝 説、もう一つは、前九年の役に従軍した八幡太郎義家と山号「鶏谷山」をめぐる伝説だ。『花栄寺沿革史』には次のように記されている。
「当寺は往古天喜(1053〜1058)年中頃(平安時代)、源義家公が奥州へ下る途中、当国米山へご参詣の折当所に下られた。山中に霊水があり休憩なさ れたところ、谷間に鶏の鳴き声が聞こえたので、共の者に訪ねたところ、草庵があり、本尊は行基(668〜749)の御作(飛鳥時代〜奈良時代)、聖観世音 菩薩像が安置されていた。」
そのころの日本は、山城の国の大和政権が勢力を伸ばし東北地方を支配下におさめつつあった。東北地方の豪族・安倍氏がこれに対抗して朝貢を怠る動きに出た ことが引き金となって、後世「前九年の役」と呼ばれる戦が勃発する。義家の父頼義も陸奥守として戦地に赴任した。義家も父につき従って北陸道を北上したの であろう。北陸道といっても現在の国道8号線ではなく、小室峠側の道を通ったことだろう。伝承によると米山薬師を参拝したとあるが、その途中で宿営地を求 めていると鶏の鳴き声で人家の近いことを知り、件の草庵を発見したしたということだ。霊水というのが何処のことであるのか? 坂又の近くであればおんめ清 水を思い浮かべるが、当時すでに湧出していたものかどうか判然としないところだ。
老僧が草庵でお守りしていたのが、行基が作ったと言い伝えられる聖観世音菩薩像とある。行基が活躍した時代からすでに300年ほども経った頃のことだが、 真偽のほどはわからない。行基自身は実在の人物であり、畿内を中心に遊行していたことが知られている。聖武天皇の招へいにより、天平勝宝4年(752)に 開眼供養された奈良の大仏様「盧舎那仏」建立のため勧進に歩いた人物だ。そのカリスマ性からか、多くのお寺や温泉地を開いたという伝説も聞くがいずれも確 たるものはない。ただ、遊行者としての行基の存在感と彼が聖武天皇の命を受け勧進に回っていた事実とから、なにがしか箔付けのために行基という名前を借り るということは充分ありえることだ。そこで花栄寺に伝わっている行基作なる聖観世音菩薩についても、同じような意味合いで受け止めておきたい。
平成24年、本尊様を修復した際に胎内から出てきた観音坐像は、いみじくもそれを物語っていた。伝承によると、「この聖観世音菩薩像は高さ8寸 (24cm)胎内秘仏として現在、花栄寺本尊の胎内に納められている」ということで、たしかに実際に胎内から姿を現したのは同じ寸法のものだった。しか し、その工法は寄木作りで時代も後世のものと思われた。行基が作ったのは一刀彫だったといわれている。
3.八幡太郎伝説と鶏谷山(けいこくざん)
八幡太郎義家が観音様をお参りした当時、草庵は「龍澤寺」といい真言宗に属していた。なぜ曹洞宗でなかったかというと、いまだ高祖道元禅師が生まれる前の出来事であり曹洞宗も存在しない頃の話だからだ。『花栄寺沿革史』では、この時のエピソードを次の筆致でつづっている。
義家は草庵を訪れ聖観世音菩薩像を拝し、老僧と一夜を明かす。帰りがけに、鶏の鳴き声を耳にしたことから山号を「鶏谷山」と命名した。
ややシンプルすぎる気もするが、色々と語り合った一夜であったのかもしれない。老僧も心づくしをしてもてなしたのかもしれない。すべては想像の彼方の出来 事であるが、出立の時に義家が一宿のお礼に「鶏谷山」という山号をつけたということが言い伝えられている。鶏の鳴き声を聞いて、深山幽谷に人の住まいして いることがわかったからだ。爾来960年にわたり、この山号が脈々と伝えられている。
4.花栄寺の開創期にかかわった人々
その後500年間の営みは記録が全くない。歴史のはざまで衰微していたといわれるが、北条毛利家の隆盛とともに再び歴史の表舞台に登場する。すなわ ち1513年、龍澤寺を改め花蔭寺(かいんじ)という禅宗寺院として開創された。時代のイメージをつかむために何人か歴史上の人物の生まれた年を比べてみ ると、まず越後の上杉謙信が1530年に生まれている。謙信とほぼ同じ時代に覇を競った代表的な3人の武将の名を重ねると、織田信長1534年生まれ、豊 臣秀吉1537年生まれ、徳川家康1543年と続き、いずれも花蔭寺開創のあと生まれている。いわば、華やかなイメージで語られることの多い戦国時代最盛 期の前夜に、花栄寺は歩みを始めたといえる。
(ア)鶏谷院殿花蔭正栄大姉
上杉謙信の父親・長尾為影は1507年(永正4)、守護大名上杉房能(ふさよし)に反旗を翻し攻め込んだ(永正の乱)。下剋上の時代、房能は松之山 天水越(あまみずごし)で部下に命を奪われてしまう。その奥方・綾子の方は北条毛利家11代当主・高広の庇護を受け、逃れたさきの女谷で伝えたのが綾子舞 といわれる。その毛利高広の御母堂が花栄寺の開基・鶏谷院殿花蔭正栄大姉である。
『花栄寺沿革史』によると「第11代北条城主北条高廣は深く曹洞宗に帰依している母(第10代北条城主北条廣春の正室、法名花蔭正栄)の願いにより、時代 と共に衰微荒廃している龍澤寺を再建し、…中略… 寺名を「花蔭寺」と改め曹洞宗に改宗させた」とある。しかし、高廣の生年がまさしく1513年の前後と されていることを考えると、高広より前の世代がお寺の開創に関わったのだろうと推測できる。
それならば、父親の廣春が開基として名を残してもよさそうだが、その栄誉は奥方に譲っているところが花栄寺の開創をめぐる不思議であり、非常に興味深いところでもある。ふたたび想像力をはたらかせ、いくつか思いつくことを挙げてみる。
まず、奥方が生まれ来る子供(のちの高廣)の成長を祈願したということが考えられる。この時代、女性がお寺を建立することはあったのかとおもって人に聞い てみたら、上越市林泉寺様の開基様は上杉謙信の姉・仙洞院だということだ。毛利家が仕えていたのが上杉家であることから、何らかの情報はあったのではない かと考えられる。
もうひとつ、お寺を建てることで信仰を隠れ蓑にして戦略的な意味を包み隠す場合も考えられる。最初に記したように、当時お寺はもっと山寄りのところにあったといわれている。
山は峠の要衝となり、隣国から攻められたときに兵を集める場所を確保する必要があったことだろう。表向きお寺という体にして、いざという時には砦としてこもることができるように備えた。そういう状況下では廣春の名前を表にしない方が良かったのかもしれない。
開基様は、死後ご尊体を花蔭寺境内南向きに埋葬された。その地と思われる個所には今日も地蔵菩薩の立像がひっそりと建ち、晴れた日の朝には林間に差し込む木洩れ陽が柔和な微笑みをたたえた尊顔を照らし出している。
(イ)御開山・曇芳文譽大和尚
前項で名前の出てきた林泉寺様の御開山は曇英慧応大和尚といい、花栄寺の本寺・普広寺(市内北条)の御開山でもある。その普広寺の第3代住職が当寺 御開山の曇芳文譽大和尚である。しかし、曇芳文譽大和尚に関する資料も精確なものが少なく、どのような人であったのかうかがい知ることは難しい。『花栄寺 沿革史』には「廣春の実弟「曇芳文譽禅師」を中興開山とし、…以下略 」という一文があり、たしかに毛利家の系譜をみると10代廣春の弟に出家者があるこ とが分かる。
しかし、同じ普広寺末寺で曇芳文譽大和尚様を御開山にいただく南鯖石石曾根の安住寺様には、石曾根帯刀の系譜として伝承されている。
5.二度の火事と本堂
花栄寺の開基家である北条毛利家は上杉謙信亡き後の後継を争う「御館の乱」(1578)に敗れ、12代景廣の時代に滅亡した。花栄寺も後ろ盾を失い 往時の勢いはなくなった。そのことについて象徴的な出来事がある。花栄寺は二度火事が起こって本堂を焼失している。一度目は室町時代末期の永禄10年 (1567)のこと。好信和尚様は「花蔭寺から出火し壮大な伽藍・書物等はほとんど焼失してしまった」と記している。しかしこの時はまだ乱の前だったた め、翌永禄11年(1568)景廣によって再建された。
ところが文化13年(1816)の火事後は事情が異なる。「5月17日夜(江戸時代)再度出火し本堂、庫裏、衆寮共に焼失してしまったが、本尊、過去帳等 大切なものは難をのがれた」とあるも、その後新たに本堂が建立されるのは文政6年(1823)、7年の時間を要した。なお、文政6年は1523年に亡くな られた御開山様の三百回忌の年にあたる。そこで、大遠忌法要に合わせて本堂の落慶を計画していたのだろうと思われる。建立当時を偲ばせるものとして、本堂 奥の間に板戸に描かれた花鳥図がある。画師が文政8年に描いたことが記されており、貴重な資料といえるだろう。
6.花蔭寺から花栄寺へ
花栄寺の紋について付言しておく。本堂屋根改修工事を経た現在の姿は、棟瓦(ぐし)が隆と立ち上がって非常に美しい。その棟瓦に3か所飾られている 梅鉢の紋が花栄寺の紋である。しかしこれは後世変更したものであり、もとは開基家と同じ一文字三ツ星であったという。御館の乱後、上杉景虎方の北条毛利家 につながる痕跡をなくす意図があり、紋の変更を余儀なくされ、天満宮を祀っていたことから梅鉢紋が選ばれたと聞く。しかし、会津に移った上杉景勝に代わっ て春日山城主に収まった堀秀治の家紋が全く同じ梅鉢紋だったため、領主と同じ紋を避けようとして若干のアレンジをほどこし、花弁と花弁の間にくさび状の突 起を付け加えている。
江戸時代中期の貞享(じょうきょう)年間(1684〜1688)、花蔭寺は花蔭正栄大姉の「栄」をいただき「花栄寺」と改名し、今日に至るまで二十七世代に渡って法燈を受け継いできた。

二十五世隨應好信大和尚晋山式並びに授戒会 昭和12年6月1日 
二十六世天真慧明大和尚晋山結制 二十五世隨應好信大和尚本葬茶昆式 昭和58年10月9日
花栄寺略年表
| 西暦 (元号) | 花栄寺に関係する出来事 | 主な出来事 |
|---|---|---|
| 1039 (長暦3) | 源義家誕生?(『中右記』の没年(1106年)より逆算) | |
| 1051 (永承6) | 前九年の役中、源義家が野田付近で宿泊 | 前九年の役(〜62年) |
| 1052 (永承7) | 行基作と伝えられる観音像の伝承 | 末法に入り、貴族中心社会に動揺深まる。念仏、阿弥陀信仰が盛んになる |
| 1053 (天喜1) | 関白藤原頼道、宇治の平等院鳳凰堂を完成 | |
| 1062 (康平5) | 源頼義が安部貞任を討ち、前九年の役終わる | |
| 1513 (永正10) | 鶏谷院殿花蔭正栄の発願により花蔭寺開創 | 北条高広生まれる? |
| 1523 (大永3) | 11月2日、当山開山曇芳文誉大和尚、示寂 | |
| 1530 (享禄3) | このころ高広が北条第11代当主となる | |
| 1549 (天文18) | 当山開基鶏谷院殿花陰正栄大姉、円寂 | |
| 1554 (天文23) | 高広、武田信玄に通じて主君上杉謙信に反抗するも、翌年降伏 | |
| 1563 (永禄6) | 高広、上野国厩橋城城主に任命される | |
| 1567 (永禄10) | 火災により伽藍焼失 | 高広、北条氏康に通じ主君上杉謙信に反抗するも、越相同盟で帰参 |
| 1568 (永禄11) | 再建 | 織田信長、足利義昭を奉じ京都にのぼる |
| 1574 (天正2) | 高広、大胡城に隠居。家督を12代景広に譲る | |
| 1578 (天正6) | 上杉謙信死去、高広は出家し安芸入道芳林と名乗る。御館の乱起こる | |
| 1579 (天正7) | 北条景広、景勝軍の武将・荻田主馬の槍を受け戦死。北条毛利家は断絶 | |
| 1687 (貞享4) | 花栄寺と改名 | |
| 1816 (文化16) | 火災により本堂焼失 | |
| 1823 (文政6) | 本堂再建 |
歴代住職
| 代 | 名前(読み) | 没年日 | 同年の主な出来事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曇芳文譽 (どんほうぶんよ) | 大永3年(1523)11月2日 | 上杉憲政誕生 |
| 2 | 朝堂瑞賀 (ちょうどうずいか) | 3月7日 | |
| 3 | 盤山顕益 (ばんざんけんえき) | 29日 | |
| 4 | 萼刕春桃 (がくりしゅんとう) | 9日 | |
| 5 | 智学昌察 (ちがくしょうさつ) | 4月4日 | |
| 6 | 演氏長祝 (えんしちょうしゅく) | 寛文12年(1672)9月23日 | 保科正之死去 |
| 7 | 石枕香寅 (せきしんこういん) | 寛文3年(1663)22日 | 有珠山噴火 |
| 8 | 海岳良刹 (かいがくりょうさつ) | ||
| 9 | 鶴應尊野 (かくおうそんや) | 正徳6年(1716)1月2日 | 吉宗8代将軍就任・享保改革開始 |
| 10 | 悟領全契 (ごりょうぜんけい) | 享保10年(1725)8月26日 | 高田藩第3代松平定輝、新井白石死去 |
| 11 | 徳峯祖孝 (とくほうそこう) | 正徳5年(1715)7月17日 | 卍山道白、ルイ14世死去 |
| 12 | 要洲龍玄 (ようしゅうりゅうげん) | 延享2年(1745)1月5日 | 家重9代将軍就任、英初代首相・ロバート・ポルウォール死去 |
| 13 | 雄山宣英 (ゆうざんせんえい) | 宝暦10年(1760)11月26日 | 葛飾北斎誕生、英王ジョージ二世死去 |
| 14 | 天産梵苗 (てんさんぼんびょう) | 文化1年(1804)3月24日 | 象潟地震、ナポレオン・ボナパルト仏皇帝就任 |
| 15 | 大法宣乗 (だいほうせんじょう) | 文化6年(1809)11月26日 | エドガー・アラン・ポー、メンデルスゾーン、リンカーン、ダーウィン、ジョルジュ・オスマン、ゴーゴリ、島津斉彬誕生 |
| 16 | 天岺運長 (てんれいうんちょう) | 文化12年(1815)4月1日 | ウィーン議定書、蘭学事始成る、井伊直弼・ビスマルク誕生 |
| 17 | 禅翁智定 (ぜんおうちじょう) | 文政7年(1824)2月7日 | ベートーベン第九初演、スメタナ誕生、バイロン死去 |
| 18 | 雲山賢龍 (うんざんけんりゅう) | 安政3年(1856)11月29日 | アロー号事件、原敬・フロイド誕生 |
| 19 | 泰山虎峯 (たいざんこほう) | 明治6年(1873)12月11日 | 太陽暦導入、キリスト教公認、津田左右吉・美濃部達吉誕生 |
| 20 | 天庵泰龍 (てんあんたいりゅう) | 明治31年(1898)12月14日 | |
| 21 | 宏菴琢禅 (こうあんたくぜん) | 昭和14年(1939)10月27日 | |
| 22 | 大法天渓 (だいほうてんけい) | 昭和13年(1938)12月5日 | |
| 23 | 俊岳謙成 (しゅんがくけんじょう) | 昭和14年(1939)4月6日 | |
| 24 | 竹外浄水 (ちくがいじょうすい) | 昭和19年(1944)12月9日 | |
| 25 | 隨應好信 (ずいおうこうしん) | 昭和58年(1983)6月16日 | |
| 26 | 天真慧明 (てんしんえみょう) | ||
| 27 | 諦光悠禅 (たいこうゆうぜん) |
お電話はこちらから0257-29-2266
お問い合わせ